「ベルトと拳銃を身につけて妻と子供たちにさよならのキスをすると、祖父は何千という人々の殺害に出かけていった――
そのことが、今でも想像できないんだ。」
ルドルフ・ヘスの孫ライナー・ヘスは言う。
ヘス家の人間の中でルドルフ・ヘスを公然と非難するのは、彼だけだ。
![]()
戦後のドイツで育ったライナーは、祖父についてほとんど何も知らなかった。
寄宿学校に入っていた彼は、ある日友達とキッチンに盗みに入って見つかり、校長に2週間庭仕事の手伝いをするよう命じられた。
学校の庭師は、ライナーだけに辛く当たった。
“ちゃんと働かない” という理由で彼だけを3ヶ月も働かせ、理由もなく彼を叩いた。
ライナーにはなぜなのか理解できなかった。 12歳の彼に、教師が恐ろしい真実を教えるまでは。
「アウシュヴィッツについても家族についても、何も知らなかった。 他の多くのお祖父さんたちと同様、
私の祖父も戦争に行ったとしか知らなかった。」
学校の庭師は、アウシュヴィッツの生残者だった。
ナチス・ドイツは占領したポーランドのアウシュヴィッツに、ユダヤ人虐殺の永久的象徴となる絶滅収容所を建設した。
初代所長に任命されたルドルフ・ヘスは、アウシュヴィッツ司令官を最長期間務めた。
彼は虐殺のピーク時には、56日間に40万人のハンガリー系ユダヤ人の虐殺を監督したことになる。
一日に7000人。
「12歳の子供にとっては、とてつもなく大きな情報だった。
祖父は家族に、大きな苦痛をもたらした。 彼の子供たちだけじゃない。 その後の何十年にも渡ってだ。
世代から世代へと、我々は同じ重い十字架を肩に背負わされる。」
ライナーの父親のハンス・ルドルフ(ルドルフ・ヘスの次男)は、反ユダヤ主義の暴力的な家庭内独裁者だった。
家は軍隊キャンプのようで、ライナーは父親に触れることすらできず、その温もりを一度として感じたことがなかった。
父親はヘスがユダヤ人虐殺に大きく関与していたことも真向から否定し、歴史は誤りで、忠実に任務を遂行していたヘスは
誤解されただけだと主張し、異論を唱えようとすれば妻と息子を厳しく罰した。
ライナーの母親は10回自殺を試み、一度はバルコニーから首を吊ろうとした。
ライナー自身も二度自殺を企てたという。
16歳で家を出たライナーは、シェフとしての訓練を積み、17歳のときに恋人(のちの妻)が妊娠したため父親になった。
ライナーの父親は息子の恋人を 「売女」 呼ばわりし、婚外子である孫をヘス家の人間とは認めなかった。
両親の離婚後、ライナーは父親とは一切連絡を取っていない。
1985年までには母親を除く家族との関係を一切断ったライナーは、ヘス家の人間には “裏切り者” と呼ばれている。
家族の前世代とは異なり、ライナーは祖父の悪行を心の奥に仕舞いこむことはしなかった。
「私の子供たちは、初めから曽祖父が誰だったかを知っているよ。 子供たちには一度も嘘をついたことはないし、
家族の過去について隠しごとをしたこともない。 長男は英語の作文の主題に、曽祖父を選んだくらいだ。
しかし私の親族は、祖父については一切話をしないと決め、ずっと嘘をつき通してきた。 責めや罪悪感に直面できないだけなんだ。
自分の前に鏡を置いて、自分たち自身をじっくり見てもらいたいよ。」
30歳までに4人の子供の父親となったライナーは、祖父に負わされた重い十字架のため眠れない夜を過ごしつつも、
家族を養うため必死で働かなければならなかった。
やがて結婚は破綻し、30代のとき二度心臓発作に見舞われた。
39歳で脳溢血を起こし昏睡状態に陥ったライナーは、生き延びて第2のチャンスを与えられたことを、
「それは自分が変わらなければならないという意味だと確信した。」
自分が起業を手伝ったケータリング・ビジネスのシェアを売り、反ネオナチ・反右翼過激派活動に飛び込み、
自分の名を善き目的のために使うことを、フルタイムの仕事にした。
初めて学校の生徒たちに話をしたのは、14歳だった息子の教師にそうするよう頼まれたときだった。
2013年には70回、学校で講演した。
反過激派組織 “Loud Against Nazis” をはじめとする、差別や偏見と戦う組織に協力している。
講演では自らの家族の過去について若者に語り、あらゆる種類の差別を排除することを訴える。
ヨーロッパに超過激主義が再生しつつあることを警告し、特に最近はドイツにおけるペギーダの動向を警戒している。
ナチズムが無くなったヨーロッパを目指す “Never Forget To Vote” キャンペーンにもその “顔” として参加し、
マイノリティーを暴力的に追放しようとする政党が強力になるのを防ぐため、反ナチの市民に投票を呼びかけた。
「反ナチの善良な人々は、政治に幻滅して投票に行かない。 でも人種やマイノリティー差別と戦うには、彼らの票が必要なんだ。」
(キャンペーンの動画はこちら)。
サイモン・ヴィーゼンタール・センターの創設者の一人であるマーヴィン・ヒアー師は、
『(ヘスの)孫がナチスのイデオロギーに従っていないのは幸運だ。 彼の活動は、ルドルフ・ヘスが
実の孫に拒絶されたことを全世界に示している。』 と述べた。
![]()
![]()
2009年の寒い朝、ライナーはヘス家の人間として初めてアウシュヴィッツを訪れた。
75歳の母親とトマス・ハーディング(『ハンスとルドルフ』著者)とイスラエル人ジャーナリストが同行した。 前夜、彼は眠れなかったという。
「到着したとき、車内には沈黙が下りていた。 怖かったよ。 その広大さが信じられなかった。 何にも触ることができなかった。」
祖父が犯した想像を絶する犯罪の現場。 すぐ隣には、父親の子供時代の遊び場がある。
ヘス司令官の邸宅では、囚人の中でも “エホバの証人” だけが屋内で働かされた。 共産主義者、政治犯やジプシーは、
屋外で働かされた。 ユダヤ人は敷地への立ち入り自体を禁止されていた。
祖父の処刑が行われた場所が、ライナーにとっては見学したものの中で最良の部分だった。
「彼はもう誰も傷つけたり罰したりできない。 処刑の前に彼は何を思ったかな?
司令官邸を、クレマトリウムを、キャンプを見て、何を感じただろう?」
“The Australian” 紙によると、ライナーのこの最初の訪問は散々だった。 ホテルの部屋を本名で予約していたため、
ホテル側は 「ヘスを名乗るものはナチスでしか有り得ない」 と警察に通報。 あからさまで強引な監視下に置かれたため、
一日過ごしただけで予定を切り上げた。
二度目の訪問ではイスラエルの学生の前に立ち、ある学生に 「もしお祖父さんに会えたらどうしますか?」 と訊かれ、
「殺します」 と答え、初めてホロコーストの生残者に握手を求められた。
(注: これが事実だとすると、『ヒトラー・チルドレン』 でのアウシュヴィッツ訪問は二度目だったことになりますね。)
彼の家族の暗い過去への旅は、2013年に “Das Erbe des Kommandanten (司令官の遺産)” として出版された。
しかし今日へス家の中でのけ者になっているのは、祖父ルドルフではなく、彼、ライナーである。
『嘘つきで、麻薬中毒で、名声とお金が目当ての、悪意に満ちた男』 というのが、叔母インゲ‐ブリットの、彼に対する評だ。
Das Erbe des Kommandanten
culminate
![]()
![]()
2013年にライナーは、疎遠になっていたヘス家の一員と苦々しい “出会い” を経験した。
それはホロコースト・フォーラムへの一通の投稿だった。
『私はオーストラリア在住の、ルドルフ・ヘスの親族です。
誇張された第二次世界大戦におけるユダヤ人迫害について、私は恥を感じてはおりません。
よその国の方が、ずっとひどく迫害されました。 スターリン時代のロシアや、鉄のカーテン時代の他国などです。
ユダヤ人は自分たちを犠牲者にし続けてきました。 そろそろ前に進むべきです。』
2013年8月7日付けの、ライナー・ヘスのオーストラリア在住の姪、アニータ・ヘスのものだった。
アニータの祖父はルドルフ・ヘスの長男クラウス。 彼の娘でライナーの従姉クリスティーンが、アニータの母親である。
「私の祖父母が植えつけたウィルスが、オーストラリアで実を結んだわけだ。 私が父方の親族と関係を持ちたくない理由が、
これで理解いただけると思う。」 ライナーは語った。
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1960年代の半ばに、ルドルフ・ヘスとヘートヴィヒの長男のクラウスは、ドイツ人妻リゾレットとともにオーストラリアに移住した。
「クラウス伯父は薬剤師助手の資格しか持っておらず、当時のドイツでは需要が少なかった。 家族に伝わるところでは、
伯父がオーストラリアに行けるようヘス家が50万マルクを用意したとのことだ。
でも祖母のヘートヴィヒは戦争犯罪者の未亡人だったため軍人恩給を支給されず、一家は極貧の生活を送っていた。
祖母は働いてもいなかった。 彼女は生涯働いたことがなかった。
だからその大金は、彼女を取り巻いていた古いナチス・ネットワークから来たものとしか考えられない。」
「15歳のクラウス・ヘスは、アウシュヴィッツの囚人を面白半分にぱちんこで撃ったため、囚人たちから嫌悪されていたよ。」
と、ルドルフ・ヘスの専属運転手を務めていた老人はライナーに語ったという。
末っ子アンネグレット(5人兄弟のうち唯一アウシュヴィッツで生まれた)の誕生を記念する家族写真では、
親衛隊隊長ハインリヒ・ヒムラーからプレゼントされた黒の親衛隊員服を着た彼は、父親の隣に立っている。
(注: ライナーの父親はヘスの次男のハンス‐ルドルフですが、彼の名は近年のニュース記事ではハンス‐ユルゲンとなっているので、
成人後改名したのかもしれません。)
![]()
![]()
![]() 庭で遊ぶハンス‐ルドルフ (ライナーの父親)
庭で遊ぶハンス‐ルドルフ (ライナーの父親)
![]()
![]()
クラウスとリゾレットはシドニーに居を定め、一人娘のクリスティーネ・ヘスを育てた。 二人はその後離婚し、クラウスは
1980年代半ばにシドニーで、長年の飲酒癖に起因する肝硬変のため死亡した。
リゾレット/クリスティーネ/アニータの三世代は、今もオーストラリアに住んでいると考えられているが、
彼らの住所はヘス家の人間の一部しか知らない。
パンナム航空とカンタス航空の貨物専門家として働いたおかげで、クラウス・ヘスは定期的にドイツに戻り、結婚式・洗礼式などの
家族の行事に参加することができた。 深酒のため、彼は家族に恥ずかしい思いをさせることがしばしばあった。
「クラウス伯父は、朝ウィスキーで歯を磨くほどだったよ。 でも触れても怒らない彼は、私にとっては持つことのなかった父親だった。
父はナチスのイデオロギーを引き継いでいたが、クラウス伯父はまったく違った。 彼が人種差別的発言をするのを聞いたことがなかった。
シュトゥットガルトの米軍基地で働いていたときは、アフリカ系アメリカ黒人の友達さえいたんだ。」 ライナーは回想する。
ライナーは、ヘス家におけるホロコースト否認の根源は祖母ヘートヴィヒ・ヘスにあると考える。
「祖母にアウシュヴィッツについて質問すると、彼女はきまって 『どうせお前には理解できないわ。 困難な時代だったから、
忘れた方がいいのよ。』 と言うだけだった。 隠すことは得意だった。 彼女の前では、強者の元ナチスでさえ
愛玩犬になった。 祖母は部屋に入ってきた瞬間から、その場を支配した。
この種の教化は、私の父ハンス‐ルドルフには効き目があった。 おそらくインゲ‐ブリット伯母にも。
ハイデトラウト伯母にも、ある程度は。 末っ子のアンネグレット叔母だけは影響されていないように見える。」
こういう状況下では、若いライナーが家族の過去について知ることは難しかった。
皮肉なことに、ライナーが大量虐殺者を取り巻く静寂を破るきっかけとなったのは、祖父へスから
子孫へと受け継がれた家財だった。
ルドルフ・ヘスは、アウシュヴィッツ司令官だった1941年から1943年の間に、親衛隊隊長ハインリヒ・ヒムラーから、
鉤十字のナチス・ドイツ国章がついた重さ30kgもある収納箱を贈られていた。
ヘスの妻ヘートヴィヒは1960年代の初めに、その箱を義理の娘であるライナーの母親に与えた。
母親から箱を受け継いだライナーは、ひとたび箱を開けるとその内容物に驚いた。
箱には人類の歴史における最も暗い章に関する、過去に公開されていなかったルドルフ・ヘスの
2100ページにも及ぶ個人的見解の記録があった。
彼が目撃した光景の詳細な記述や、抹殺の過程がどのように改善できるかの計画書があった。
ヘス一家のアウシュヴィッツにおける理想的な生活をとらえた600枚以上の写真、50枚のカラー・スライド、弾薬の箱、
衣類、煙草のホルダー、印章入りの金の指輪、ヘスが愛する家族に宛てて書いた手紙などもあった。
「祖父の書類はアウシュヴィッツに勤務した人々や班の正確な記述も含んでいた。」
アウシュヴィッツで監視兵を務めた親衛隊員は8000人に上る。 なのに刑を受けたのはそのうちのわずか41名に過ぎず、
そのことが未だに信じられないライナーは言う。 彼はまた、アウシュヴィッツ職員だった数多くの元親衛隊員が、
戦後ドイツに戻って本名のまま銀行重役や医師の職に就いたことに不満を感じている。
ルドルフ・ヘスの箱は、現在ミュンヘンにある現代史研究所に保管されている。
(注: ということなので、『ヒトラー・チルドレン』 に出てきたあの箱のことのようです。)
「何もかもが一致する。 アウシュヴィッツ生残者の供述は、祖父のような親衛隊員の報告書を裏づけている。
輸送されてきた人々の記録には、それと呼応する強制労働キャンプの記録がある。
ヒトラーは 『我が闘争』 で自分の計画を記述しているし、ゲッベルスは “ユダヤ人がいなくなった” ドイツについてオープンに書き、
日記には大きな輸送の記録をつけていた。 警察の記録がこれらをすべて裏づけている。
これでもなお、アウシュヴィッツの恐怖を否定するというのだろうか?」
信じられないといった面持ちで、ライナーは自問する。
ルドルフ・ヘスの第3子で次女のブリギッテ(インゲ‐ブリギット)は、ライナーを除くと唯一の、
悪名高いヘスについて公に話をする家族の一員だ。
過去40年をワシントンで暮らしてきた彼女は、癌の診断を下され闘病中である。
彼女はヘス家に関するライナーの著作を快く思っていない。
「ライナーがしたことは、本当にひどいことよ――彼はあの頃まだ生まれてもいなかったのだから、何の話をしているのかすらわかっていないわ。
すべてお金のためよ。 最初彼は、あの箱をイスラエルのヤド・ヴァシェムに売ろうとしたの。 そして今度は、
この本で金儲けをしようとしている。 彼は麻薬をやっているに違いないわ――普通じゃないもの。
あまりにも頭にきて、あの本は最後まで読むことができなかったわ。」
ブリギッテは、ヘスの子供たちはキャンプ内に入ったことは一度もなかったし、彼らの邸宅は一度も臭ったことがなかったと主張する。
「キャンプ内で何が起こっているかなど、まったく知らなかった。 誰もね。 クラウスが囚人をぱちんこで撃ったなんてのもでたらめよ。
庭や屋内に囚人はいたけれど、そして彼らと遊んだこともあったけれど、キャンプに入ったことは一度もなかったわ。
私たちは、単に子供が普通することをした――遊んだの。 私は7歳か8歳だったけれど、煙が上っているところも、
庭のイチゴに灰がかかっているところも、見た覚えがない。 ライナーは信じ難い嘘つきよ。」
現在ワシントンに住むブリギッテには、ユダヤ人の友人も多くいる。 しかし彼女は、ホロコーストの犠牲者数に疑問を持ち続ける。
彼女の寝室の壁には、愛する父親の写真が掛かっている。
「父は本当に愛情深い人だった。 彼にはふたつの面があったに違いないわ。 私たちは一度も見ることのなかった面が。」
ブリギッテはヒトラーの戦争犯罪は赦し難いことだと認めるし、アウシュヴィッツで起きたことも否定しない。
しかし彼女の父親とドイツを貶める裏工作があったと信じている。
「ナチスは散々悪く書き立てられるわ。 他の誰も、そんな風には扱われないのに。 父は唯一の存在ではなかった。
至るところにさらに上の者がいて、彼らはもっとひどい悪人だった。
父は私に、もし当局が彼に 『犠牲者数は5百万人だったと言え』 と命じていたら、そう言っていただろうと言ったわ。
クレマトリウムは、戦後きれいに修復されたの。 暗い力が暗躍したのよ。」
「連合軍ですか?」 とインタビュアーに訊かれたブリギッテは、「イエス」 と答えた。
ブリギッテは、父親が処刑前に書いた回想録を一度も読んでいない。 全く興味が持てなかった。
子供時代の思い出の地であるアウシュヴィッツにも一度も戻っていないし、そのつもりもない。
「年を取りすぎたし、病も重すぎるわ。」
ブリギッテは長兄クラウスの元妻リゾレット(アニータの祖母)と現在も連絡を取っている。
しかし彼女は、シドニーに渡ったアウシュヴィッツ司令官の子孫の住所を明かすつもりはない。
ライナー・ヘスは何度もアニータの所在地をつかもうとしたが、その度に失敗している。
ヘスの長女ハイデトラウトは、世界的に有名なホロコースト否定論者であるロバート・フォーリソン(Robert Faurisson)の
インタビュー・パートナーを、定期的に務めてきた。 感謝のしるしとして、ブリギッテはフォーリソンに、
ヘス一家のアウシュヴィッツでの写真を贈った。
ブリギッテもハイデトラウトも、孫たちにヘス家の歴史の暗い部分について話すつもりはない。
ヘス家の歴史は、必要がある場合のみ教える。 それが基本だ。
Dr. Robert Faurisson
オーストラリアで成功したように、ホロコースト否定の根が次の世代に実を結ぶことを願いつつ。
ルドルフ・ヘスの長男クラウスは1980年代半ばにオーストラリアで死没し、次女ブリギッテはワシントンで闘病中。
残る3人は?
認知症を発症した長女ハイデトラウトは、ドイツ北部に住んでいる。
ライナーの父親ハンス‐ルドルフはヘス家とは疎遠になり、その後ドイツ北部の宗教セクトのメンバーとして暮らしているらしい。
三女のアンネグレットも、ドイツ北部に住んでいる。
4人の子供(息子2人と娘2人)が成人した今、ライナー・ヘスはシュトゥットガルト近郊の小さな町 Weil der Stadt の
アパートメントに一人で暮らしている。 孫もすでに2人いる。
「ネオナチや極右集団との戦いは、将来どのような展開になると思いますか?」 との問いに対する、ライナーの答え。
「右翼過激集団は馬鹿じゃない。 ゆっくりと、しかしとても効果的に、地盤を固めつつあります。
ですが今日の若者は私に希望を与えてくれます。 彼らは祖父の時代の若者ほど簡単には騙されないでしょう。
だから将来にはポジティブな展望をもっています。 ただ、ひとつだけ確かなことがあります。 毎日が苦労の連続だということです。
人権というものは、我々が立ち上がって戦わない限り、保証されないのです。
断固として戦い続けます。 機会があるときは、いつでもね。」
《 つづく 》
![にほんブログ村 海外生活ブログへ]() にほんブログ村
にほんブログ村
 )
)


 小麦畑がこんなにキレイだったなんて、知らなかった・・・!
小麦畑がこんなにキレイだったなんて、知らなかった・・・!


 この金物屋さん、葬儀屋さんも兼ねているからかぁ。
この金物屋さん、葬儀屋さんも兼ねているからかぁ。 










































 の多い話題
の多い話題  をお届けすることにしますね。
をお届けすることにしますね。 


























 」
」 

 なんちゃって。
なんちゃって。 


















 トマス・ハーディング
トマス・ハーディング




















































































 庭で遊ぶハンス‐ルドルフ (ライナーの父親)
庭で遊ぶハンス‐ルドルフ (ライナーの父親)






 つい、思ってしまいます。
つい、思ってしまいます。


 エルダド・べック。 相反する二つの主張。
エルダド・べック。 相反する二つの主張。
































































 )
)

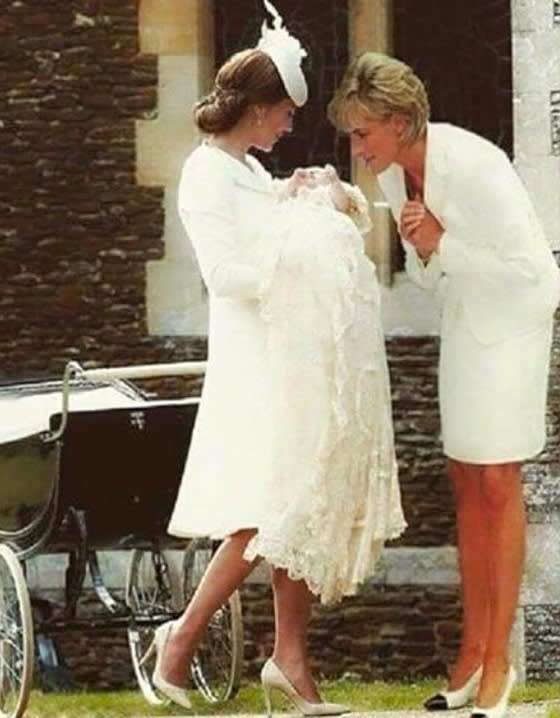


 )
)





































































































































































 下右が、そのお宅。 奥の森のようなところから出てきたわけです。
下右が、そのお宅。 奥の森のようなところから出てきたわけです。











































 「あそこに人がいる」 と知らなければ肉眼ではほとんど見えないくらい小さい3人です。
「あそこに人がいる」 と知らなければ肉眼ではほとんど見えないくらい小さい3人です。










